糖尿病とは
 膵臓から分泌されるホルモンで血中の糖を細胞内へ移すことで血糖値を下げる働きを持つインスリンが、十分に機能しなくなることによって血糖値が高い状態が継続するようになります。そうすると、動脈硬化が進行し、腎障害、神経障害、聴覚障害などに繋がるだけでなく、心筋梗塞や脳卒中などの重大な疾患の発症リスクも高まります。
膵臓から分泌されるホルモンで血中の糖を細胞内へ移すことで血糖値を下げる働きを持つインスリンが、十分に機能しなくなることによって血糖値が高い状態が継続するようになります。そうすると、動脈硬化が進行し、腎障害、神経障害、聴覚障害などに繋がるだけでなく、心筋梗塞や脳卒中などの重大な疾患の発症リスクも高まります。
疲れやすくなる、のどが異常に乾くようになるといった自覚症状が有名ですが、ほとんど自覚症状が現れずに健康診断によって初めて糖尿病の発症が分かるケースも多いと言われています。
糖尿病内科について
 糖尿病をお持ちの方は年々増加しており、今や国民病とも呼ばれています。高血糖な状態が続くと、腎症、神経障害、網膜症といった三大合併症だけでなく全身に合併症が起こるリスクがありますので、注意が必要です。日本では2型糖尿病をお持ちの方が糖尿病全体の95%を占めていますが、長い間症状が現れないために治療せずに放置してしまい、合併症でお悩みの方が多くいらっしゃいます。
糖尿病をお持ちの方は年々増加しており、今や国民病とも呼ばれています。高血糖な状態が続くと、腎症、神経障害、網膜症といった三大合併症だけでなく全身に合併症が起こるリスクがありますので、注意が必要です。日本では2型糖尿病をお持ちの方が糖尿病全体の95%を占めていますが、長い間症状が現れないために治療せずに放置してしまい、合併症でお悩みの方が多くいらっしゃいます。
当院では、糖尿病を適切にコントロールすることで合併症の発症を防ぐことを目標とし、お客様それぞれの病状に応じた最適な治療方針をご提案することで、お客様と二人三脚で生活習慣も考慮した綿密な治療をご案内しております。
当院の治療法
糖尿病の治療にあたっては、
- バランスの取れた食事
- 適度な運動習慣
- 最適な薬物療法の3点を意識することが大切です。
当院では、お客様の生活習慣やお身体の状態を考慮して、最適な食事・運動習慣を検討させて頂きます。
また、薬物療法を実施する場合は、注射薬や飲み薬などからお客様にとって最適なものを処方いたします。
糖尿病に伴う
合併症の評価を行います
発症の初期段階では、健康診断で尿中の糖の存在や血糖値の高さを指摘される程度で、はっきりとした自覚症状は乏しいことが多いと言われています。こうした状態を長期間放っておくと、慢性的に血糖値が高い状態が続くことで全身の血管に負荷がかかり、様々な合併症に繋がる恐れがあります。
三大合併症
全身の毛細血管に負担がかかることが原因となりますが、初期段階では自覚症状が乏しく、定期的に検査を受けることが大切となります。
神経障害
三大合併症の中で一番最初に現れるものです。火傷や怪我の痛みを感じない、手足がしびれるといった手足の末梢神経障害の症状が起こるようになります。
また、胃腸の不調、筋肉に萎縮、筋力低下、立ち眩み、発汗異常など、様々な自律神経障害が起こることもあります。
網膜症
眼球の中の網膜の血管に異常が起こり、浮腫や眼底出血が起こります。初期段階では見え方には異常が見られずに、眼底検査によって初めて異常が発見されるケースがほとんどです。見え方に異常が無い場合でも、眼科で定期的に眼底検査を受けることで、早期発見と早期治療によって失明を予防することが可能です。
網膜症は、緑内障に続き日本における失明の原因の第2位となっており、白内障の発症リスクも高まると言われています。
腎症
腎臓はザルのような働きをしていますが、動脈硬化によって腎障害が進行すると、尿中に蛋白が流出するようになります。尿検査によって蛋白の流出を確認し、また、血液検査によって腎機能の状態を確認します。 腎症が進行すると、腎機能がストップして腎不全へと繋がり、透析治療を要することとなります。なお、人工透析に繋がる原因として、糖尿病腎症が最も多いと言われています。
その他の合併症
心筋梗塞、脳卒中、脳梗塞、感染症、皮膚病、下肢閉塞性動脈硬化症など。
当院では、心電図、腹部エコー、CAVI(血管年齢測定)などをお客様の状態に応じて実施することがあります。
糖尿病の治療
 糖尿病の治療法は、お客様それぞれの病状に応じて異なります。なお、食事や運動といった生活習慣の見直しが最も重要であり、お客様と二人三脚で継続的に取り組むことが可能な方法を検討していきます。薬物療法を必要とする場合は、お客様の病状、ご年齢、生活習慣を考慮した上で最適な方法を検討していきます。また、必要に応じてインスリン注射をご提案する場合もあります。糖尿病は、高脂血症や高血圧を併発していることも多いため、それらの治療も同時並行で行っていきます。
糖尿病の治療法は、お客様それぞれの病状に応じて異なります。なお、食事や運動といった生活習慣の見直しが最も重要であり、お客様と二人三脚で継続的に取り組むことが可能な方法を検討していきます。薬物療法を必要とする場合は、お客様の病状、ご年齢、生活習慣を考慮した上で最適な方法を検討していきます。また、必要に応じてインスリン注射をご提案する場合もあります。糖尿病は、高脂血症や高血圧を併発していることも多いため、それらの治療も同時並行で行っていきます。
糖尿病を適切にコントロールして、お客様が少しでも快適な生活を送って頂けるよう、当院スタッフ一丸となって誠心誠意サポートさせて頂きます。
糖尿病療養指導
血糖測定方法のご説明やインスリン注射、日常生活におけるお悩みなどを伺い、治療に対するやる気が継続できるようにサポートさせて頂きます。
糖尿病療養指導
- インスリン自己注射
- 血糖自己測定
- 日常生活の注意点
- 低血糖について
- その他、生活に関するご相談
糖尿病栄養指導
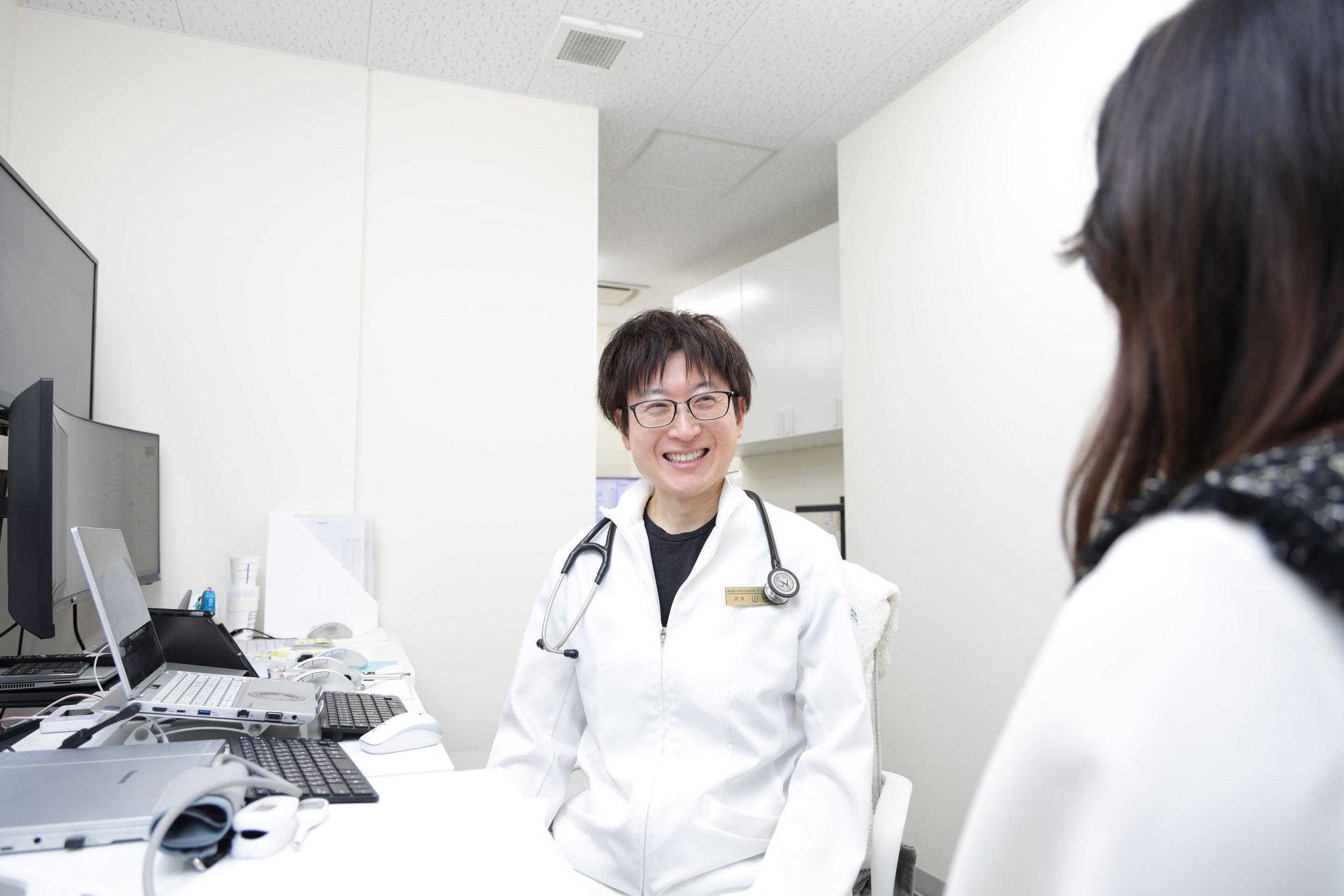 医師の指導の下で、高血圧、脂質異常症、糖尿病などの病状を改善するために食生活の見直しが必要となるお客様については、個別の栄養相談も実施しております。
医師の指導の下で、高血圧、脂質異常症、糖尿病などの病状を改善するために食生活の見直しが必要となるお客様については、個別の栄養相談も実施しております。
お客様のライフスタイルや家族背景などを伺い、継続的に実施可能な食事習慣をお客様と二人三脚で検討していきます。これまでの生活習慣を徐々に改善することで、健康的な生活が送れるようにご支援いたします。
HbA1c値が高いと
診断された場合
糖尿病リスクを確認するために、HbA1c(ヘモグロビン・エー・ワン・シー)という検査を行います。運動や食事によって血糖値は短期的に変動する特徴があり、HbA1cによってブドウ糖とヘモグロビンの結合割合をチェックします。この結合割合は、直近1〜2か月間の血糖値の実測値と連動しているため、HbA1cを検査することで直近1〜2か月間の血糖値の平均を把握することが可能となります。
HbA1cの値が高いということは直近1〜2か月間の血糖値も高いということを示します。なお、特定保健指導における基準値は5.6%未満となっています。HbA1cが6.5%以上の場合は糖尿病の疑いが強い状態であり、速やかにブドウ糖負荷試験などで状態を確認することが大切です。また、7.0%以上の状態が慢性化すると合併症のリスクも上昇するため、至急適切な治療を受けるようにしましょう。
HbA1c値と合併症
HbA1cが高いということは、血管へ常時負荷がかかっているということを示しています。糖尿病の三大合併症である糖尿病性腎症・糖尿病網膜症・糖尿病性神経障害などの細小血管障害だけでなく、動脈硬化によって引き起こされる心筋梗塞・脳梗塞・狭心症・閉鎖性動脈硬化症などの大血管障害といった合併症が起こるリスクが高まりますので、注意が必要です。
特に、足に潰瘍が起こる確率が上がる糖尿病性足病変、認知症、歯周病などについては糖尿病によって悪化するリスクが高まると考えられています。このような疾患の発症および進行を防ぐために、血糖値を適切な値に管理することは極めて重要となります。
また、糖尿病だけでなく甲状腺機能亢進症、異常ヘモグロビン症、腎不全などによってもHbA1cの値が高くなると考えられています。したがって、HbA1cの値が正常でないと分かった時点で速やかに専門医へ相談することで、様々な病気の早期発見・早期治療に繋げていきましょう。
「糖尿病で足がだるい…」
その症状、放置していませんか?
糖尿病の方の中には、「足がだるい」「重い」「しびれる」 といった症状を感じる方が少なくありません。
これは 血糖値のコントロール不良や合併症 が原因となっている可能性があります。
糖尿病と足のだるさの関係とは?
糖尿病が進行すると、血管や神経がダメージを受けることがあり、その影響で足のだるさやしびれが現れることがあります。
主な原因は以下の通りです。
糖尿病神経障害
糖尿病による合併症の一つで、 高血糖が長期間続くことで神経が損傷 し、足の感覚異常やだるさを引き起こします。
- 初期症状:足のしびれ、チクチクする痛み
- 進行すると:感覚が鈍くなり、ケガや火傷に気づかないことも
対策
- 血糖値のコントロールが最優先(HbA1cを適正範囲に保つ)
- ビタミンB12の摂取(神経の修復を助ける)
- 適度な運動で血流を改善する
血流障害(糖尿病性末梢動脈疾患)
糖尿病により動脈硬化が進むと、足先まで十分な血液が届かなくなることがあります。
- 特徴:長時間歩くと足が重くなる、冷たく感じる
- 進行すると:潰瘍(傷が治らない)や壊疽(細胞が壊死)につながる
対策
- 定期的に血流チェック(病院でのABI検査が有効)
- 足のマッサージやストレッチを習慣に
- 禁煙する(喫煙は血管をさらに狭くする)
筋力低下や運動不足
糖尿病の人は運動不足になりやすく、筋力低下による足のだるさを感じることがあります。
- 特徴:長時間歩くと足が重くなる、冷たく感じる
- 進行すると:潰瘍(傷が治らない)や壊疽(細胞が壊死)につながる
対策
- ウォーキング・ストレッチで足の筋力維持
- 座りっぱなしを避ける(30分ごとに立ち上がる)
- 栄養バランスのとれた食事を心がける
こんな症状がある場合は要注意!
「ただの疲れ」と思っていても、次のような症状がある場合は、糖尿病の合併症が進行している可能性があります。
- 足のしびれや痛みが強くなってきた
- 傷ができやすく、治りにくい
- 足が冷たく、青紫色になっている
- 長時間歩くと足が痛くなる(間欠性跛行)
- 足の感覚が鈍く、触られてもよくわからない
糖尿病が原因で足の血流や神経に異常がある場合、早期の治療が重要です。自己判断せず、早めに専門医を受診しましょう。
足のだるさを予防するための習慣
糖尿病の足の症状を悪化させないために、日常生活で意識すべきポイントをまとめました。
血糖値を適切に管理する
- HbA1cを 7.0%以下 に保つことが目標
- バランスの良い食事(GI値の低い食品を選ぶ)
- 適度な運動で血糖値を安定させる
足のケアを徹底する
- 毎日足のチェックをする(傷や異常がないか確認)
- 保湿クリームで乾燥を防ぐ(ひび割れ防止)
- 靴選びに注意する(圧迫や摩擦を避ける)
血流を良くする
- 適度な運動(ウォーキングや軽い筋トレ)
- 入浴で足を温める
- 足を高くして寝る(むくみ防止)
糖尿病の足のだるさを放置しないで
病院を受診しなくても 風邪を予防することが最も大切 です。
- 足のだるさは糖尿病の初期症状の可能性あり
- 糖尿病神経障害や血流障害が原因のことが多い
- 血糖値コントロールと血流改善が重要
- 症状が悪化する前に当院で相談を!
糖尿病の足のだるさは放置すると深刻な合併症につながる 可能性があります。「最近足が重いな…」と感じたら、早めに対策をしましょう!
Q & A
糖尿病の治療薬はどんな種類のものがありますか?
大きく分けると、飲み薬が7種類、その他注射薬に分けられます。
飲み薬は、膵臓に働きかけてインスリンの分泌量を増やすもの、インスリンの抵抗性を向上させるもの、尿中への糖の排出を促進し血糖値の低下を促すもの、腸から緩やかに糖を吸収しやすくするものなどがあります。このようなお薬の中から、お客様のご年齢、腎機能、肥満度を考慮して、最適な処方を行います。
糖尿病を患っている人はどれくらいいますか?
2016年の国民健康・栄養調査によると、糖尿病の疑いがある方は約1,000万人、糖尿病の可能性が0ではない方は約1,000万人いると報告されています。
糖尿病になったら定期的に受けた方が良い検査はありますか?
血液検査によって血糖値やHbA1cを測定し、糖尿病のコントロール状況を確認することが大切です。また、尿検査による腎機能障害の進行度合いの確認、CAVI/ABI検査による動脈硬化の進行度合いの確認、腹部エコー検査による脂肪肝の合併有無の確認もお勧めしております。
関連ページ
- 糖尿病とは
- 糖尿病とインスリン
- 糖尿病の3大合併症
- 糖尿病の検査
- 食事療法と運動療法
- 高齢者の糖尿病
- 妊娠糖尿病
- 生活習慣病外来 蒲田で生活習慣病の予防と治療をお考えの方へ
- 健康診断
- 医院紹介
- 医師紹介
- 当院の特徴
- 求人案内
監修者プロフィール
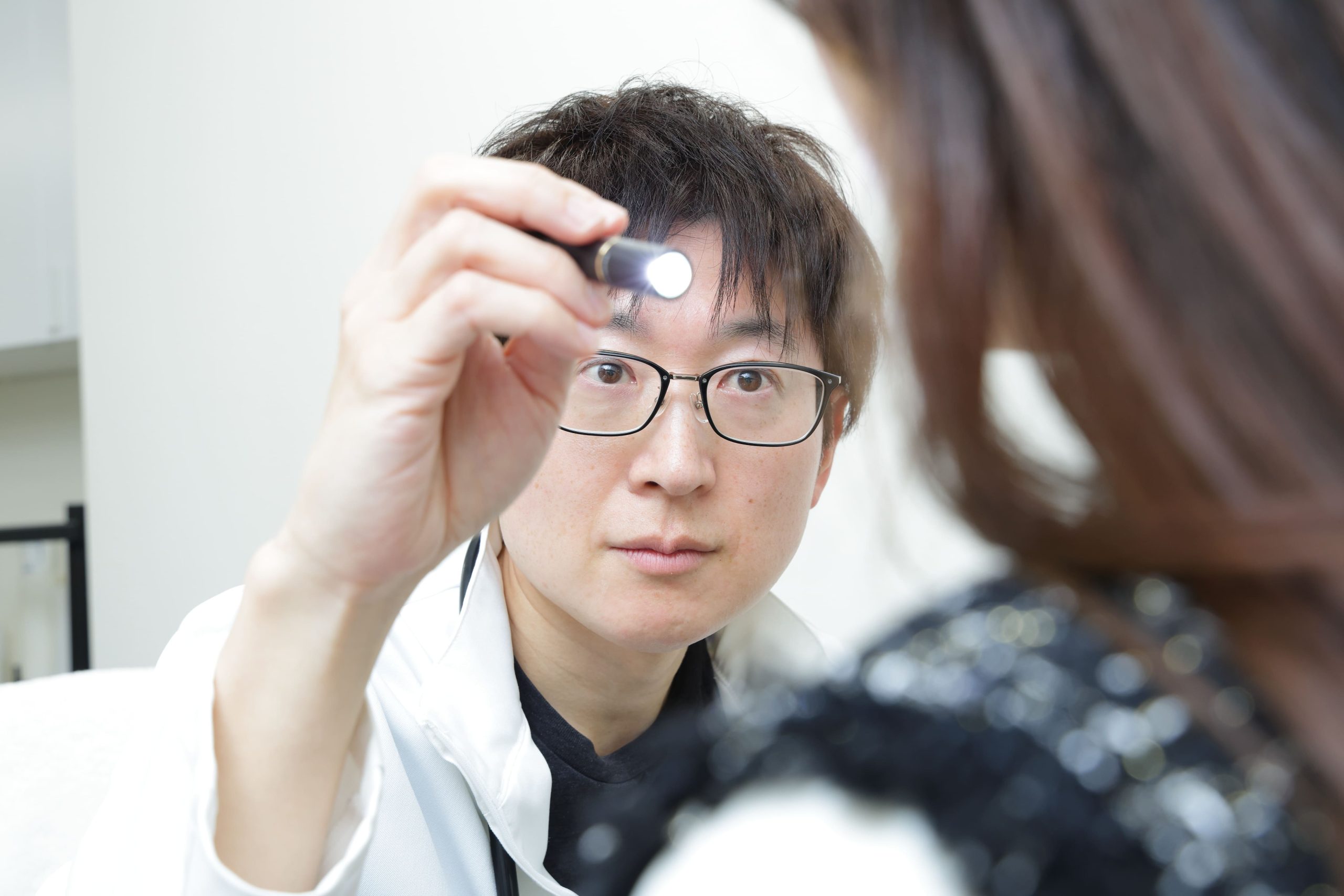 院長 山田 朋英 (Tomohide Yamada)
院長 山田 朋英 (Tomohide Yamada)
医学博士 (東京大学)
山田院長は、糖尿病・甲状腺・内分泌内科の専門医であり、東京大学で医学博士号を取得しています。東大病院での指導医としての経験や、マンチェスター大学、キングスカレッジロンドンでの客員教授としての国際的な研究経験を持ち、生まれ故郷の蒲田でクリニックを開院しました。
資格・専門性
- 日本糖尿病学会認定 糖尿病専門医・研修指導医
- 日本内科学会 総合内科専門医
豊富な臨床と研究の経験を活かし、糖尿病や甲状腺疾患における最新の治療を提供しています。
最新更新日:2025年3月16日










